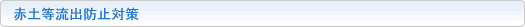 |
 |
�y����z
���Ǝ��{���O�̓쑤�ɂ��鍌�삩��ԓy�����C��֗��o���Ă��܂��B
���여��̍k��n�i�T�g�E�L�r�����j����Ȕ������ƂȂ��Ă��܂��B
�i���J���̍���̂r�r�Z�x��1600�`2500mg/l�ɂ��Ȃ�܂��B�j |
| ���V���̍��� |
|
���J���̍��� |
 |
 |
 |
|
|
|
| �W�����J�ɂ��A���Ƃ����є������獌��Ԑ�������o���Ă��܂��I |
|
�y�V�Ί_��`���Ǝ��{���ɂ������Ȑԓy�����o�h�~��z
�V�Ί_��`���݂ɂ�����ԓy�����o�h�~��́A�@����������A�Z���r�E�����r�̐ݒu��B�@�B������������{�Ƃ��A�ȉ��̂悤�ȑ���s���܂��B
�Q�l �� ��������Ƃɂ�����ԓy�����o�h�~��v |
 |
�P�D�����̔�����}����
�\�y�����ډJ�H�̗������Ȃ��悤�ɗ��n�ʂ����Ƃɂ���Đԓy���̔������ڂ����~�߂܂��B |

|
�@ |
�ނ��o���̗��n���A�V�[�g�Ŕ핢���邱�Ƃɂ�蒼�ډJ��ԓy�ɐG��Ȃ��悤�ɂ��܂��B
���ʁA�ԓy�̑����̔������}�����܂��B |
| �@ |
 |
�@ |
���n�̌͂ꑐ����ԓy���ނ��o���Ă��镔���ɂ��Ԃ��邱�Ƃɂ��A�ԓy�̑���������}���܂��B
���}���`���O�̉�� |
| �@ |
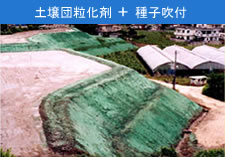 |
�@ |
�E�y��c������
�y����ł߂��p�̂����܂��U�z���܂��B
�E��q���t
�@�ʂ̈���Ƒ����h�~�̂��߂Ɏ�q�𐁂��t���A�A����蒅�����܂��B
��q���t�́A��q�����炷��܂ł́A�@�ʂ̈���Ƒ����h�~�̌��ʂ��������߁A���炷��܂ł̖@�ʂ̈���Ƒ����h�~�̌��ʂ�y��c�����܂ŕ₢�܂��B |
| �@ |

|
�@ |
�ł�A�����邱�Ƃɂ��A�@�ʂ̈���Ƒ����h�~�̌��ʂ�����܂��B
|
|
| �@ |
�Q�D����������Z���r�⒲���r�Œn���Z��������
���������������A�Z���r�⒲���r�Œn���Z�������鎖�ŁA�ԓy���C�ɗ���o���̂�h���܂��B
�܂����ݒ����r�̐Z���\�͂���~�J�����������ꍇ�́A�@�B�����p�����Q�Tppm�ȉ��ɏ������č���ɕ������܂��B
|
|
| �@�@�y�Z���r�A�����r�̏ꏊ�z |
|
|
| �@ |
�R�D�H�����H�v���A�y���̗��o��}���܂��B
�H���ɂ����闇�n�ʐς����������A�ԓy�̗��o��}���܂��B
�N�x���Ɏ{�H����G���A�����߂Ă����A�{�H��͌��n�̐A�����ŗΉ����邱�ƂŐԓy�̗��o��}���܂��B |
| �@ |
|
|
| �@ |
| �@ |
| �@ |
| �@ |
 |
|
|
 |